どうもanjinです!
今日は管理会計分野の『シェアードサービス』について書きます。あまり聞き慣れない言葉かと思いますが、大企業で取り入れているところもあります。基礎部分から解説していきます。
【シェアードサービスとは】

シェアードサービスとは、経営学用語の一つで、『複数のグループ企業からなる企業が、人事・総務・経理・法務・情報システムなどの間接部門を担う部署を一か所に集約させる企業改革のこと』です。
シェアードサービスの対象となる業務は、経理部門や財務部門の一般会計業務や財務業務、総務部門や人事部門の給与計算業務や社会保険業務、情報システム部門のヘルプデスク業務などです。
日常的に大量の取引を処理する業務や、月末や月初めなど特定の日に偏って大量の処理が必要な業務、専門的なスキルを必要とする業務をやっていた部署をグループ内の1つの部門でまとめることにより、業務の効率化やコスト削減、クオリティの向上などさまざまな効果が期待できます。
【シェアードサービスの目的】

シェアードサービスの最大の目的は、『経営力の強化』にあります。グループ企業各社で共通する間接業務はシェアードサービスに集約します。下記のような効果が期待できます。
- 業務の効率化
- 標準化した業務の知識を蓄積
- グループ企業の運用
- 外部にサービスを供給できるチャンスが生まれる
また、人事や設備のコストを抑えられるため導入・運用に成功すれば費用対効果が高まるでしょう。
しかし一方で、場合によってはこれまでの慣習を捨てなければならないことも。強いリーダーシップのもとに企業全体で改革を推し進める力量が必要になります。
【シェアードサービスの起源】

経営手法としてのシェアードサービスの起源は、米国のGE(ゼネラル・エレクトリック)社が導入したケースが最初だといわれています。
各部門にあった伝票処理などの経理業務を1つの部門に集約し、各部門における業務簡素化を実現する目的で実施されたのが始まりでした。
その後、ERP (Enterprise Resource Planning 企業資源計画)が米国の大企業などで導入されたことにより、シェアードサービスの活用は拡大しました。
日本では、1997年の純粋持株会社解禁以降に法整備が進んでグループ経営が推進されるようになってから、多くの企業が積極的に導入するようになりました。
バブル崩壊後の不況や情報技術の発展を背景に、業務の集約化や標準化を図り、コスト削減などを実現する目的でシェアードサービスが活用されています。
【シェアードサービスとアウトソーシング/BPOの違い】
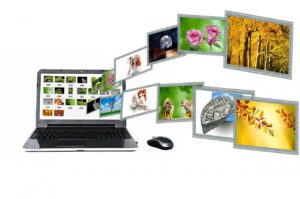
シェアードサービスと似た制度として、アウトソーシングやBPOがあります。
どのような違いがあるか、下記にて説明します。
アウトソーシング
アウトソーシングとは、外注や業務委託のことであり、自社内で行っていた業務を社外の会社やスタッフに委託することをいいます。
直接利益とは結び付かない業務を外注することで、コア業務に注力することを目的としています。
シェアードサービスはグループ会社間で共通部門を共有することで、アウトソーシングは社外に業務を委託するという点が異なります。
グループ内に部門を集約するシェアードサービスでは、知見やノウハウは社内に蓄積されていきますが、社外に委託するアウトソーシングではノウハウの蓄積が難しいという点も大きな違いです。
BPO
BPOとは、「Business Process Outsourcing」の略称です。
つまり、BPOもアウトソーシングの一種です。ただし、一般的なアウトソーシングとは委託する業務の範囲が異なります。
アウトソーシングで委託される業務が総務や経理などの間接部門の一業務であるのに対し、BPOでは開発やマーケティング、業務設計や経営分析など企業の根幹にかかわる業務を部門ごと外部企業に委託します。社外業者に自社組織の一部を置いてもらうイメージです。
また、アウトソーシングはあくまでも業務のみの外注です。委託することで結果的に業務の効率化が実現したとしても、効率化までが委託範囲に入っているわけではありません。
一方、BPOにおいては委託における運用方法、プロセス設計、課題解決の提案や結果分析といった範囲まで委託内容に含まれます。部門にかかわる業務すべてを社外に置くことがBPOの特徴です。
【シェアードサービスのメリットとデメリット】

〈シェアードサービスのメリット〉
企業がシェアードサービスを導入することで得られるメリットは、下記3つになります。
業務の効率化
間接部門が行う専門的な業務をグループ内の一か所に集約することにより、業務の効率化が期待できます。
これまで部門ごとに行っていた入力業務や印刷業務を集約し、さらにフォーマットや運用方法、締め切り期日などを統一することで、業務の効率化を実現することができます。
コスト削減
グループ内の間接部門を一つに集約することで、それぞれの部門で個別にかかっていた人件費や機材設備が共有化され、コストを大幅に削減できます。
水道光熱費はもちろん、会議室などの施設費用、複合機やパソコン周辺機器などの備品や消耗品のコストも抑えられます。
業務品質の向上
専門的な業務を行う部門が集約するため、業務の最適化が進み、業務品質の向上も期待できます。
また、各部門が行っていたスケジュール管理も一か所に集中するため、業務の納期遵守率の向上も期待できます。
シェアードサービスのデメリット
シェアードサービスを採用することで考えられるデメリットは、下記3つになります。
初期費用が高い
シェアードサービスの設立には、子会社などのグループ会社に集約する方法や、本社などの企業組織の一部門に統合する方法などがあります。
どの方法も各部門の既存業務を標準化し、部分最適化されている業務システムを共通化する必要があり、そのための業務工数やシステム導入費などの初期費用がかかります。
また、シェアードサービスを導入する拠点は、土地の価格などを考慮することはほとんどなく、本社の近くに設置する傾向が見られます。その理由として、「早期立ち上げのため現状の場所を活用」、「コミュニケーションの維持」、「書類などの円滑な受け渡し」などが挙げられます。
シェアードサービス導入にかかる初期費用の高さは大きな障壁となります。規模の大きなグループ企業の場合、間接部門の規模も大きいため、初期費用も膨れ上がってしまいます。シェアードサービスを採用する場合は、事前に綿密な資金計画が必要です。
運用開始までに時間がかかる
シェアードサービスの導入から運用開始までには長い時間を要します。各部門やグループ各社で独自に設定されているルールやシステムを統合する必要があるため、一つ一つ手法の聞き取りをしながら整備を進めなければなりません。
一度導入したシステムをグループ内で標準化し、集約するのには時間も費用もかかります。また、採用している社内システムが複雑な場合、その内容を理解するための人員配置にも考慮が必要です。
これらの事前準備を省いてシステム共有化をすぐに推進する場合もあるようですが、現場の混乱を招き、本来の目的であったはずの業務効率化を図ることができなくなる恐れがあるため、慎重に進める必要があります。
モチベーションの低下
間接部門の業務には、データ入力や印刷業務、書類管理などの単調な処理や作業内容が多く、配置された社員によってはモチベーションが低下してしまう恐れがあります。反復的なオペレーション業務が続くことで、優秀な人材を流出させてしまうことも考えられます。
人員を配置する際には、社員のモチベーションが維持できるように、業務プロセスの可視化や将来のキャリアパスの明確化などの対応が必要です。
【各部門のシェアードサービス活用例】

シェアードサービスの対象領域としては、経理・財務、人事、IT(情報システム)、購買が挙げられました。各領域におけるシェアードサービスの活用例を紹介します。
経理・財務
経理・財務の領域では、具体的に売掛金・買掛金、経費精算、入出金伝票管理、仕訳といった法令で定められた手順・業務を標準化・システム化する傾向が見られます。一般会計については、グループ会社で個別に行うよりも、シェアードサービス化して定型的なプロセスにまとめた方が効率化が図れるからです。
一方、管理会計や内部監査といった専門性の高い分野はシェアードサービス化が難しい分野と言われます。
人事
人事業務では給与・賞与計算、社会保険、福利厚生といった手続きでシェアードサービスの活用が有効です。採用や配属、人事制度の構築といった直接業務に関わる部分ではなく、定型化しやすいプロセスに着目していきます。
IT・情報システム
情報システムもシェアードサービスの恩恵が得られやすい領域です。専門的な知識が必要となるハードウェア管理やソフトウェア管理を集約し、また、ヘルプデスク等もまとめて運営できるようにします。セキュリティに関するポリシー策定や管理作業を一括で行えば、スキルの不足した人材がグループ各社で行うよりも、セキュリティの強化が図れます。
購買
購買業務においても、オフィス備品文房具などをまとめて調達するようにすれば、グループ各社が個別に管理するよりもコストが削減できることが期待されます。加えて、設備管理・資産管理といった手間のかかる作業も、シェアードサービスによってノウハウを蓄積し、業務の効率化を図ります。
【まとめ】

シェアードサービスは、グループ企業の規模が大きいほどコスト削減やクオリティの向上が期待できる手法です。
導入には、ある程度の初期投資と長期的な改革が必要ですが、その分成功した場合のメリットは計り知れません。
検討する最高は、メリットもデメリットも理解したうえで導入することが重要です。
【参考書籍】
以上が本日のテーマになります。ご覧頂き、ありがとうございました!







コメント