どうもanjinです!
今日は会計分野の『ストックオプション』について書きます。ストックオプションてよく聞くけど、いったい何なの?という方いると思いますので、基本部分中心に解説していきます。
【ストックオプションとは】

ストックオプションとは、『株式会社の従業員や取締役が、自社株をあらかじめ定められた価格で取得できる権利』です。
まず、会社が従業員や取締役に対して、あらかじめ定められた金額(権利行使価格)で、会社の株式を取得できる権利を付与します。従業員や取締役は、将来、株価が上昇した時点でストックオプションの権利を行使します。その時点で、会社の株式を権利行使価格で取得し、その後、時価で株式を売却することになります。権利行使価格と株価上昇分の価格との差が、利益として得られるという報酬制度です。従業員や取締役への報酬額が、その会社の業績向上による株価上昇と連動します。そのため、ストックオプションの権利を付与された側にとっては、業績向上したときの、実質上のインセンティブにもなります。
【ストックオプションの歴史】

元々ストックオプションとは、アメリカで株式や社債を販売するために魅力付のアイテムとして利用されていた制度です。その他、ストックオプションを用いて有能な経営者を招き入れ、破産企業の再生を行う為にも行使されていました。アメリカでは、1950年の税制改正によって従業員・取締役に税務上の恩恵が与えられた為、一気に拡大していった制度です。
日本では、1997年までストックオプションという制度は認められておらず、実務界では新株引受権(会社が発行した株式を優先的に引き受ける権利)を行使した擬似ストックオプション制度をソニーやソフトバンクが取り入れていました。こうした実務界のニーズや、当時株価が大幅に下落したことを受けて1997年、景気対策の一環として商法上初めてストックオプションという制度が設けられました。
しかし、この時点では、まだ付与対象者や発行数に制限があったりといくつかの使い勝手の悪さがありました。そういった点を改善するために「新株予約権」という権利をつくり、ストックオプションの制度を改善したのです。
この新株予約権のうち、インセンティブ目的で社員や取締役に対して付与される場合が一般的にいう「ストックオプション」です。社員や取締役に新株予約権が付与された場合は、税務や証券取引上でいくつかの優遇処置が認められている為、非常に有利であるというイメージがつきました。
【ストックオプションの仕組み】

ストックオプションの概要について触れてきましたが、より理解を深めてもらうため具体的な事例をあげながら仕組みを解説していきます。
ストックオプションは企業が導入する報酬制度のうちのひとつですが、企業の株価や業績と連動している点が大きな特徴です。
例えば、営業職の売上成績に応じて支払らわれるインセンティブ制度があります。
インセンティブの評価の対象となるのは、あくまでも個人の営業成績です。
しかし、ストックオプション制度は市場における自社の株価によって利益(報酬)が決まるのです。
例えば、株価が1株500円であったとします。そして、企業が特定の従業員に対して、3年間は1000株まで300円で購入できる権利(ストックオプション)を与えたとします。
このストックオプションの権利を従業員に与えることを「権利付与」といいます。
業績が好調で市場の株価が1株800円に上がったとしても、ストックオプションの権利を持っている従業員は1株300円で購入することができるのです。
実際に、企業の業績が好調で株価が上昇した場合、購入した価格と売却した価格の差分が従業員の利益となります。
ストックオプションの権利を使って株を購入することを「権利行使」、その株を売ることを「株式売却」といいます。
先程の例で説明すれば、市場の株価750円を250円で購入できるので、1株あたり500円の利益が生まれることになります。
もし、1000株の権利を行使したのであれば、500,000円(利益5000円×100株)の利益が出ることになります。
一方で、業績が悪化して株価が上がった場合であっても、ストックオプションの権利を行使しなければ良いだけです。
先程の例のとおり、「3年間は1000株まで300円で購入できる」権利が与えられますので、この期間内に取引を完了させれば良いのです。
このように、通常の株取引とは違い、従業員が損失を受けにくい仕組みになっているのもストックオプションの大きな特徴です。
【ストックオプションの種類】

ストックオプションは大きくわけると、付与されるときにお金がかからない「無償ストックオプション」とお金がかかる「有償ストックオプション」の2つに分類されます。
無償ストックオプションは「無償税制適格ストックオプション」と「無償税制非適格ストックオプション」に分けられ、無償税制非適格ストックオプションの活用型として「1円ストックオプション」という仕組みもあります。また有償ストックオプションの活用型として、「信託型ストックオプション」という仕組みもあります。
どのストックオプションを発行すべきかは、それぞれの種類の特徴を把握しなければなりません。それぞれのストックオプションの特徴について解説します。
無償税制適格ストックオプション
ストックオプションは原則として、給与所得として扱われます。そのためストックオプションを利用して得た利益については税金が発生します。無償税制適格ストックオプションは、付与対象者が行使期間などについて厳しい要件を満たすことで、権利行使時の課税を免れる制度です。
無償税制非適格ストックオプション
無償税制非適格ストックオプションは無償税制適格ストックオプションのような要件がなく、権利行使時に給与課税が発生します。無償税制非適格ストックオプションの場合最大約55%の給与課税が適用されるので、どちらを選ぶのかはとても重要です。
1円ストックオプション
1円ストックオプションとは行使価格を1円に設定した、無償税制非適格ストックオプションの活用型です。権利行使時にその時点の株価とほぼ同等の利益が得られる仕組みで、退職金として使われるケースが多いです。
無償税制非適格ストックオプションと異なる点としては、課税が最大約55%の給与課税ではなく最大約25%の退職金課税ですむ点です。また権利行使時の金銭的負担が少ないので、権利を行使しやすい点もメリットです。
有償ストックオプション
有償ストックオプションは無償オプションと違い、付与されるときにお金がかかります。会社が発行したストックオプションを、従業員が発行価格で購入することで権利が付与されます。
無償税制非適格ストックオプションでは最大約55%の給与所得課税が付与されますが、有償ストックオプションでは最大約20%の譲渡課税のみが課されます。そのため有償ストックオプションの方が、税率は低くなります。
信託型ストックオプション
有償ストックオプションの活用型として、信託型ストックオプションというものがあります。発行したストックオプションを全員分まとめて信託に預け、満了期間まで保管します。保管されている期間にストックオプションに交換できるポイントを従業員に付与し、ポイントに応じてストックオプションが割り当てられるという仕組みです。
信託型ストックオプションは近年登場した新しい仕組みで、割当先を後から決められる点などがメリットです。
【ストックオプション制度の導入方法】

ストックオプション制度の導入方法には、下記のように8つのステップがあります。
- 株主総会で取締役への付与を決議する
- 募集事項を定める
- 申込者へ通知を行う
- 付与予定者と割当数を定める
- 登記する
- 払込みを受ける
- 事業報告書に記載する
- 就業規則への規定、周知、労働基準監督署への届出
①株主総会で取締役への付与を決議する
取締役に対してストックオプション制度を導入する際は、株主総会を開き、ストックオプションの金額や内容などについて決議する必要があります。
ただし、株主総会開催義務には例外があるのです。
- 定款にて、取締役に対するストックオプション制度の取り決めが明記されている
- 社員に対して付与する
などの場合、株主総会の決議は不要となります。ストックオプションの付与対象によって、株主総会の開催要否が変わる点に注意してください。
②募集事項を定める
次に、募集事項を定めます。検討すべき事項は、
- ストックオプションの権利行使価格
- 権利行使期間
- ストックオプションの数量
さらに、
- ストックオプションと引き換える形で金銭の払い込みを必要としない場合には、その理由
- ストックオプションと引き換える形で金銭の払い込みを必要とする場合には、その払い込み金額、もしくは算定方法
- ストックオプションの割当日
なども募集事項として定める必要があるのです。
公開会社における手続き方法
ストックオプション制度の導入に関して、公開会社が気を付けなければならない点があります。
通常ストックオプションを導入する場合、公正な価額で発行するために、本来は株主総会で決定するものを取締役会での決定で済ませることができます。
注意したいのは、株主に対して株主総会当日の2週間前までに募集事項を通知、または告知しなければならないという点。
通知や告知は、
- 官報
- 日刊新聞紙
- 電子広告
を使って行います。
非公開会社における手続き方法
非公開会社における手続き方法では、2つほど注意点があります。
- 公正発行・有利発行どちらの場合においても、募集事項決定に関しては、原則、株主総会の特別議決が必要になる
- さらに非公開会社で注意が必要なのは、有利発行の場合、株主総会で取締役が有利発行で募集する必要性について説明する義務がある
非公開企業は、この2点を注意してストックオプションの導入を進めてください。
③申込者へ通知を行う
3つ目は、申込者に対する通知。
- 上場企業
- 非上場企業
どちらの場合でも、企業はストックオプション制度に申し込んだ者に対して、
- 株式会社の商号
- 募集事項
- ストックオプションの権利行使の際、金銭の払い込みの必要がある場合には払い込みを取り扱う場所
について通知する必要があるのです。
一方、ストックオプション制度に申し込んだ者は、
- 申込者の氏名、および住所
- 申し込みをするストックオプションの数
について、会社に書面を提出します。
④付与予定者と割当数を定める
申込者に対する通知が済んだら、次は付与予定者と割当数を定めていきます。こちらも、
- 上場企業
- 非上場企業
どちらでも、
- 申し込みをした者の中から割り当てる者を定める
- かつその者の割当数を定める
ことが必要です。
ただしこのステップは、割当を行う日の前日までに、申込者への事前通知が必要となります。
もし付与予定者が、ストックオプション制度を設計した段階で決定していた場合は、付与予定者と事前に引受契約を交わすことを条件にして、省略することも可能です。
⑤登記する
ここまでのステップが済んだら、次のステップは登記です。こちらも、上場企業・非上場企業のどちらの場合でも、ストックオプションを発行したら、企業は割当日の当日から2週間以内を期限として、ストックオプションについての登記を行います。
⑥払込みを受ける
ストックオプションの割当を受けた場合該当者は、
- 払込み期日
- 権利行使期間の初日
までに会社が決定、通知した銀行などの金融機関に振り込み金額の全額を払い込まなければなりません。なお、払い込みが行われない場合、ストックオプションの権利は消滅します。
⑦事業報告書に記載する
公開会社は、ストックオプションについて事業報告に記載します。
- 事業年度末時点
- 取締役を含む役員がストックオプションを保有している場合
という条件下で、事業報告書に、
- ストックオプションの内容
- 保有人数
などを記載するのです。
⑧就業規則への規定、周知、労働基準監督署への届出
ストックオプション制度を導入したら、
- 就業規則への規定作成
- 労働者への周知
- 労働基準監督署への届出
も併せて必要となります。この手続きが終了して初めて、ストックオプション制度の導入ステップが完了となるのです。
【ストックオプションのメリット、デメリット】

ストックオプションのメリット4つ
ストックオプションは、採用、支払い、資金調達など、あらゆる面でメリットがあり、ベンチャー経営において非常に重要な資本政策となっています。メリットは、下記4つになります。
①優秀な人材の採用のための活用
ストックオプションは、将来的な株価の上がり幅によっては大きなキャピタルゲインとなるので、優秀な人材にも魅力的なインセンティブ制度としてアピールできます。
さらに入社後も、ストックオプションの行使が可能になる時点より前に辞めた場合は報酬がもらえないので、優秀な人材の流出を防ぐこともできます。
②従業員のモチベーションアップ
ストックオプションは、自社の株価が上がるほど、つまり業績がアップするほどキャピタルゲインが大きくなります。
そのため、役員や従業員は「会社の業績をあげる」という一つの目標に向かうため、モチベーションを高めることができます。
③社外協力者との長期的な付き合いが可能
ストックオプションは、従業員のみならず、社外協力者(顧問・アドバイザー・業務委託など)に対しても付与できます。
外部の協力者にストックオプションを付与することで、権利行使まで長期的な付き合いが可能となります。また、上記メリットの2つ目と同様の理由で、社外協力者の当事者意識を高め、モチベーション向上にも繋がります。
さらに、ストックオプションで報酬を支払うことで、キャッシュアウトを防ぐことができるというメリットもあります。
④株式の持分の回復ができる
株式の持分比率が下がっている経営陣にストックオプションを付与して、早めに行使することで、持分を回復してから上場に臨むという活用法もあります。
ストックオプションのデメリット4つ
デメリットは下記4つになります。
①株価が行使価格を下回った場合、従業員の士気低下に繋がる
株価が行使価格を下回った場合、つまり、ストックオプションの権利を行使してもキャピタルゲインが得られない状況になった場合は、インセンティブ制度として機能しないため、従業員の士気が低下してしまう可能性があります。
この状況は、自社の努力とは関係なく起こる可能性も十分にありうるので、将来への見通しが重要です。
②付与基準が不明瞭な場合、従業員に不公平感が発生する
付与基準が不明瞭なままストックオプションを運用していくと、付与対象者以外の従業員が不公平感を感じたり、士気を無くしてしまうことに繋がる可能性があります。
また、このことをきっかけに、従業員間の関係性が悪化する危険性もあるので、運用には十分な注意が必要です。
③報酬を得た人材が流出する
ストックオプションの権利を行使してキャピタルゲインを得た場合、ストックオプションに魅力を感じていた従業員にとっては、その会社で働き続ける理由が減ってしまいます。
今の会社より良い条件の会社があった場合には転職する従業員が出てくる可能性もあります。
④既存の株式に希薄化が生じる
上場後にストックオプションを大量に付与してしまうと、会社に入ってくるお金が無い状態で株式の発行数が増加することになり、既存株主が保有している株式の価値が低下してしまいます。
【まとめ】
ストック・オプションは、上場会社だけでなくベンチャー企業などの非上場会社でも活用することができます。十分な報酬・給与を支給する資金的な余裕がないなか、報酬・給与の補填的な意味合いでストック・オプションを付与するわけです。
しかし、十分な知識がないまま発行をしてしまうと、後々トラブルにつながることがあります。たとえば、評価算定をしないままでいると有利発行として認定されてしまい、課税対象となってしまうことがあります。
ストック・オプションの活用を検討する際には、税理士等に相談してアドバイスを受けてから発行するようにしましょう。
[参考書籍】

立場別・ステージ別 ストック・オプションの活用と実務〈第4版〉
以上が本日のテーマになります。ご覧頂き、ありがとうございました!


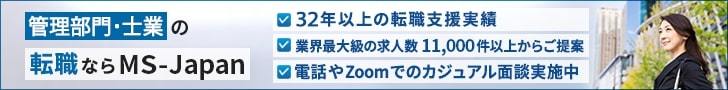


コメント