どうもanjinです!
今日は労務分野の『雇用保険』をテーマにします。前回、社会保険の『介護保険』を取り上げましたが、今日は労働保険になります。いつも通り、基礎的部分から説明していきます。
【雇用保険とは】

雇用保険とは、『労働者が失業した場合や働き続けるのが困難になった場合、また自ら教育訓練を受けた場合に生活と雇用の安定、就職の促進を図るために給付などを行う制度のこと』です。
また、雇用保険は、政府が管掌する強制保険制度であり、労働者の生活および雇用の安定と就職の促進を目的にした保障が受けられる労働保険です。労働者は事業主とともに負担し、負担料率は事業主側が高く設定されています。
現状、女性や高齢者の労働参加を促す目的により、雇用保険の適用範囲も拡大されています。
雇用保険は強制適用保険制度のため、加入条件を満たした人は雇用保険への加入が義務づけられています。
【雇用保険制度について】

雇用保険制度には、主に下記2つの事業があります。
《雇用安定事業》
1つ目は、従業員が失業をした際に生活の安定と就職の促進のための給付や、教育訓練を受ける者のために給付する『雇用安定事業』です。
雇用安定事業には事業主に対する助成金や、中高年齢者などの再就職しにくい求職者に対する再就職支援、若者や子育てしている女性に対する就労支援があります。
助成金には若年者や中高年の試行雇用を促進する「試行雇用奨励金」や、高齢者や障害者を雇用する事業主を支援するための「特定求職者雇用開発助成金」、創業や雇用を増やす事業主を支援する「自立就業支援助成金」や「地域雇用開発助成金」などがあります。
《能力開発事業》
2つ目は、失業の予防や雇用状態の是正および雇用機会の増大、労働者の能力の開発および向上その他労働者の福祉の増進などをはかるための『能力開発事業』です。
これらの財源は、上記の問題の解決が経営者や企業に利益をもたらすであろうということで、経営者や企業からの保険金のみで運営されています。
【雇用保険の目的】

雇用保険の目的は、『労働者の失業対策を含めて労働者の雇用環境・失業状態を安定させるため』にあります。
人はいつ失業するかわかりません。
企業が事業を継続できなくなり急に解雇された、ということは誰にでも起こり得ます。次の仕事が見つかるまでは無収入で生活するには困りますので、「雇用保険」により援助がうけられます。
「雇用保険」とは、失業時に受け取れる失業保険の給付、企業に勤めているときに受けられる育児休業給付、介護休業給付、教育訓練給付などの被保険者の生活を守るための保険です。次の仕事が見つかるまでの間、「雇用保険」の一つである「求職者給付」(いわゆる失業保険)を受ければ、それで暮らすことができます。
「雇用保険」は主に国の厚生労働省が管理しているため、手続きや給付は各地のハローワークがおこなっています。
【雇用保険の加入条件】

失業者の生活安定のために必要な雇用保険ですが、全ての労働者に加入資格があるわけではありません。
雇用保険に加入するためには、
- 勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあること
- 1週間あたり20時間以上働いていること
- 学生ではないこと(例外あり)
の3つの条件を満たす必要があります。以下、各条件について説明していきます。
(1)勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあること
ここでいう「31日間以上働く見込み」には、31日間以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、すべてが該当します。
例えば、雇用契約の際に取り交わした契約に「更新する場合がある」旨の規定があり31日未満で雇い止めすることが明示されていないときは、「31日間以上働く見込み」があることになります。
また、雇用契約に更新規定がない場合でも、労働者が実際に31日以上雇用された実績があるときは、この条件が適用されます。
(2)1週間あたり20時間以上働いていること
これは「所定労働時間」が週20時間以上ということを意味します。
従って、一時的に週20時間以上働いたことがあったとしても、契約上の所定労働時間が週20時間未満となっている場合は、この要件時間を満たしません。
(3)学生ではないこと(例外あり)
原則として学生は雇用保険に加入できません。
ただし、卒業見込証明書を有する者であって卒業前に就職し、卒業後も引き続き同一の事業主に勤務することが予定され、一般労働者と同様に勤務し得ると認められる場合は、雇用保険の加入対象者となります。
つまり、学生が企業から内定をもらい、卒業前からその企業で勤務をスタートさせ、引き続き同じ企業で勤務を続けることが明らかである場合には、雇用保険加入の対象になるということです。また、通信教育、夜間、定時制の学生も雇用保険加入の対象者となります。当然この場合も上記の(1)と(2)の条件を満たすことが必要です。
以上の(1)〜(3)が雇用保険加入のための条件になります。雇っている労働者が雇用保険加入の対象者になるかどうかは、契約時の所定労働時間や更新規定の有無、実際の勤務期間がどのように定められているかで判断します。
学生の場合は、学生だから一様に加入できないとするのではなく、昼間か夜間か、定時制学校の学生かどうかなどをきちんと確認しなければなりません。
【雇用保険料の負担割合】

従業員に対して様々な給付を行うために、雇用保険では事業者・従業員の両方から保険料を徴収しています。従業員の「賃金」の額に一定の料率を掛けた額を保険料として納めることになり、料率は年度ごとに決められています。なお、事業によって保険料率が異なり、従業員の保険料負担は「失業等給付」部分のみとなるが、事業者は失業等給付に加えて「雇用保険二事業」部分の保険料も負担することになります。
2019年4月1日から2020年3月31日までの雇用保険料率は次の通りとなる。
【雇用保険料率】
・「一般の事業」の雇用保険料率:0.9%
従業員負担:0.3% 事業主負担:0.6%
・「農林水産・清酒製造の事業」の雇用保険料率:1.1%
従業員負担:0.4% 事業主負担:0.7%
・「建設の事業」の雇用保険料率:1.2%
従業員負担:0.4% 事業主負担:0.7%
※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。
【雇用保険の加入手続き】

雇用保険へ加入するためには「労働保険保険関係成立届」を、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に提出する必要があります。都道府県および市町村、農林水産、建設、港湾労働法の適用される港湾での港湾運送に該当する事業についてはハローワークに提出します。
従業員を雇った場合の手続き
初めて雇用保険の適用対象となる従業員を雇うこととなった場合は、前述の「労働保険保険関係成立届」を提出して、保険関係成立に関する手続を済ませた後、事業所を管轄するハローワークに届出書を提出します。
提出する届出書は「事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」であり、受理印を押された「労働保険保険関係成立届」の事業主控と確認書類などを添えて、「雇用保険適用事業者設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」となります。
その後、新たに雇用保険の対象となる従業員を雇った場合は、そのたびに事業所を管轄するハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する必要があります。
「雇用保険被保険者資格取得届」を提出すると、ハローワークから「雇用保険被保険者証」が交付される。この「雇用保険被保険者証」は雇用保険に加入した従業員本人に渡す。
雇用保険の対象となる従業員を雇った場合の手続きは、従業員が被保険者となった日の属する月の翌月10日以内に行う必要があります。
なお、個人経営の農林水産業で、雇用している労働者が常時5人未満の場合は、雇用保険の適用は任意だが、労働者の2分の1以上が加入を希望するときは、加入の希望をしていない労働者を含み加入要件を満たす労働者全員分の加入の申請が必要となります。
給付金を従業員が受け取る場合の手続き
「高年齢雇用継続給付」や「育児休業給付金」「介護休業給付金」などを従業員が受ける場合には、それぞれの申請書を事業所を管轄するハローワークに提出する必要があります。
従業員の離職時の手続き
雇用保険に加入していた従業員が離職した場合、雇用保険の被保険者でなくなった日の翌日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書(離職票)」を事業所を管轄するハローワークに提出する必要があります。
なお、離職証明書の離職理由について事業主と離職者との間で主張が異なる場合などは、ハローワークにおいて事実関係を調査します。
それぞれの手続きには確認書類が必要で、確認書類には賃金台帳、労働者名簿、タイムカードなどの出勤簿なども含まれるので普段からきちんと管理しておくことが大切です。
また、ほとんどの届出書は労働基準監督署またはハローワークのサイトよりダウンロードできるが、複写式となっている「労働保険保険関係成立届」などは労働基準監督署で、「雇用保険被保険者離職証明書」、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」などはハローワークで直接受け取る必要があります。
【雇用保険における給付金の種類】

雇用保険で支給される給付金にはいくつか種類があります。下記において、雇用保険の種類と支給される条件について解説します。
求職者給付・就職促進給付
失業した際に、新しい仕事を探している期間中の収入を保障したり、再就職を促進したりするための給付金です。このうち、一般的に「失業保険」などと呼ばれる基本手当は離職前6ヶ月間に支払われた通常の賃金(ボーナスなどを除く)の合計を180で割って算出した額(賃金日額)の50~80%を1日当たりの支給額(基本手当日額)として、その90日~360日分が支給されます。何日分の支給が受けられるかは、離職理由や被保険者期間、年齢によって異なります。なお、基本手当日額には、上限額も決められています
| 基本手当日額の上限額(令和2年3月1日現在) | |
|---|---|
| 30歳未満 | 6,815円 |
| 30歳以上45歳未満 | 7,570円 |
| 45歳以上60歳未満 | 8,330円 |
| 60歳以上65歳未満 | 7,150円 |
基本手当を受けるためには、離職前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上(離職理由によっては離職前の1年間に6ヶ月以上)あることが必須条件です。またこの給付金は「働く意思と能力がある求職者」に支給されるものなので、住民票のある地区のハローワークに離職票などを提出し、求職活動をしなければ支給されません。
なお、基本手当は、ハローワークに求職の申込みをした日から7日間(待期期間) 、また、離職理由によっては最大3ヶ月間(給付制限期間)は支給されません。そのため、退職後は、なるべく早めにハローワークでの手続きをおこなうことが重要です。
高年齢雇用継続給付金
雇用保険に加入していた期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者について、60歳以降の賃金が60歳時点の賃金と比較して75%未満に低下した状態で働き続ける場合に「高年齢雇用継続基本給付金」が支給されます。この給付金は、賃金の低下率によって支給率が異なり、最大で各月の賃金の15%相当額が支給されます。これ以外にも、60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」もあります。
育児休業給付金
1歳または1歳2ヶ月(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6ヶ月または2歳)未満の子どもを養育するために育児休業を取得した被保険者に支給されます。休業の間に会社から賃金が支給されない場合、給付金の額は、原則として、休業開始時の賃金の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)相当額となっています。
介護休業給付金
家族の介護のために休業した被保険者に支給される給付金です。原則として、休業開始前6か月間の賃金合計額を180で除した額(賃金日額)の67%相当額が休業した日数分だけもらえます。同じ家族に対しては93日分を限度に3回まで支給されます。
教育訓練給付金
国が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、受講料や入学料などの教育訓練経費の一部を支給する制度です。教育訓練給付金をさらに分けると、「一般教育訓練給付金」「特定一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」の3つがあり、それぞれ支給対象となる教育訓練・受給資格・給付額が異なります。これらの給付金を受けるには、受講開始日までの間に同一の事業主に引き続いて雇用されていた期間が3年以上(※初回受給の場合は1年以上)あることが条件となります。
《参考書籍》
以上が本日のテーマになります。ご覧頂き、ありがとうございました!
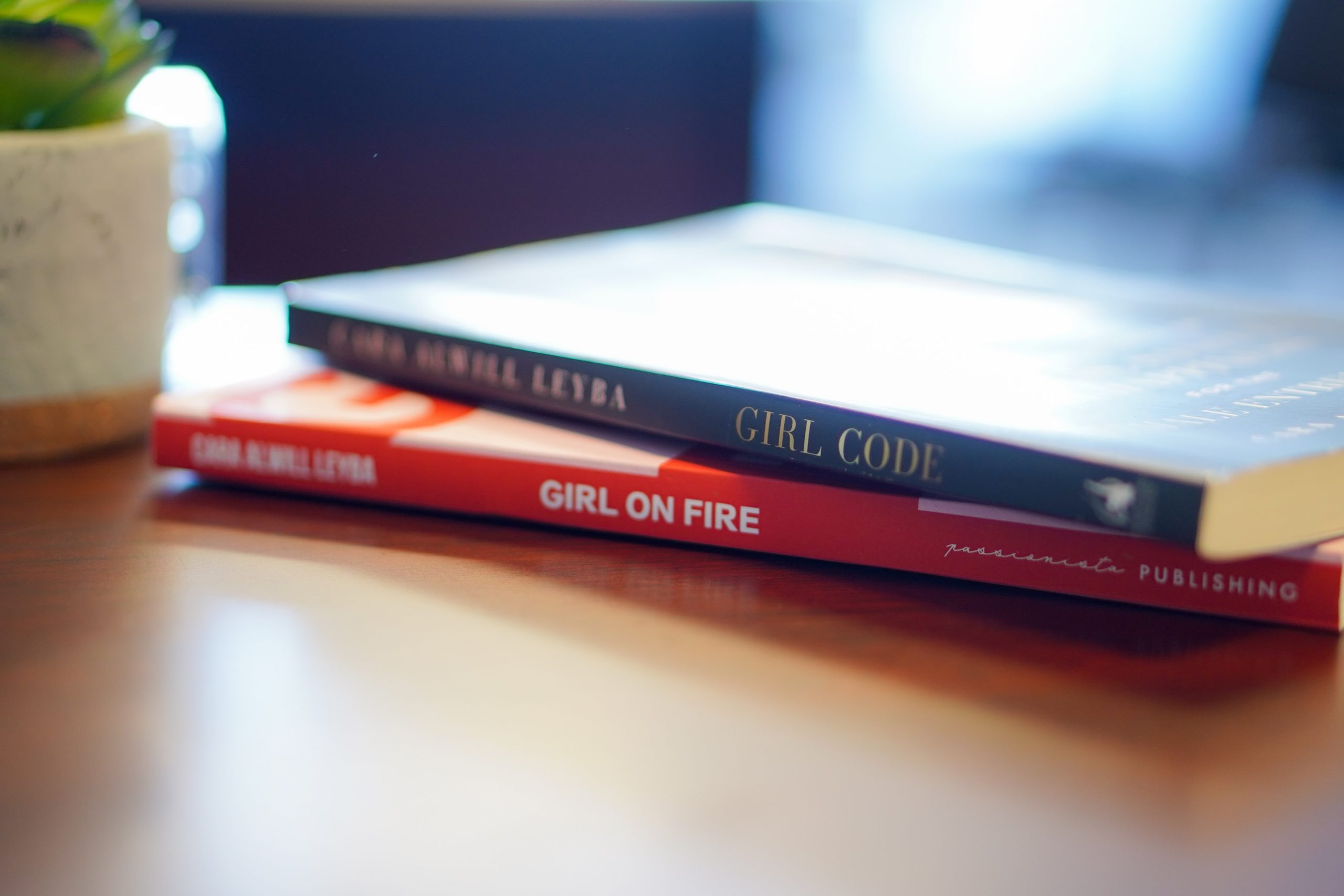

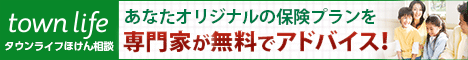



コメント